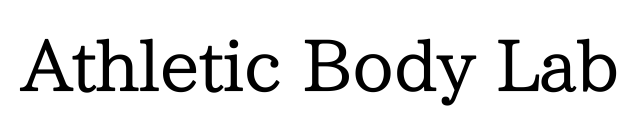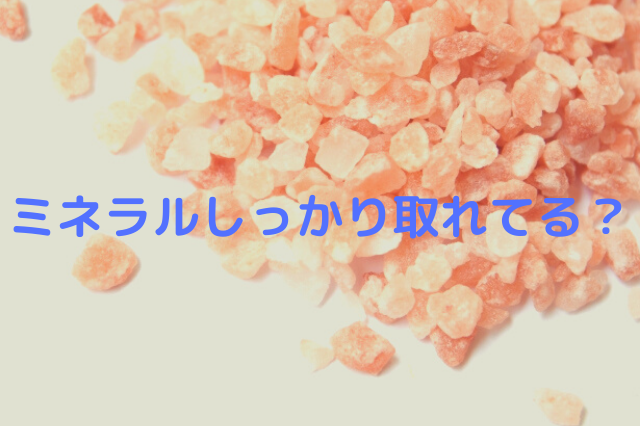「ミネラルが大切!」
よく耳にする言葉かもしれませんが、実際のところミネラルについて聞かれると、なかなか答えづらいですよね。
今回はミネラルに関して、種類や重要性、またオススメの食材などを書いていきたいと思います。
Contents
ミネラルって何?

ミネラルとは、5大栄養素のうちの1つです。
一般的な有機物(炭水化物・タンパク質・脂質など)に含まれる4大元素である炭素・水素・酸素・窒素以外の必須元素のことを言います。
名前の由来は、mine(鉱石)やmetal(金属)などから来ています。
そんなミネラルは、動植物から作り出すことはできません。
よって、水や土壌から吸収したミネラルを持った物質を人間が食事として摂食しています。
(ミネラルを豊富に含んだ土からは、良い野菜が摂れるのはこのこと)
種類は?

地球上には、114個の正式名称を持ったミネラルが存在します。
その中でカルシウム、マグネシウム、リン、ナトリウム、カリウム、マンガン、ヨウ素、コバルト、硫黄、塩素、リン、モリブデン、セレン、鉄、銅、亜鉛の計16種類が人間の体内に存在し、また欠乏症が明らかになっています。
ここでは必須ミネラル分類分けをしていきます。
主要ミネラル(7種類)
主要ミネラルとは、体重1g当たりの体内濃度が1mg以上含有しているミネラルのことです。
体内にあるミネラルの99%はこれにあたります。
多量ミネラル
カルシウム、リンの2種類が多量ミネラルです。
体重1g当たりの体内濃度が10mg以上含有しているのが特徴になります。
少量ミネラル
マグネシウム、カリウム、ナトリウム、塩素、硫黄の5種類が少量ミネラル。
体重1g当たりの体内濃度は1〜10mgです。
微量ミネラル(9種類)
体重1g当たりの体内濃度が1〜100μg(マイクログラム)以上含有しているミネラルを言います。
鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン、コバルトの9種類存在します。
体内ミネラルでは約1%の存在です。
まとめると
以上をまとめると、こんな感じになります。
「多量ミネラル(7種)」
(多量元素)
・カルシウム
・リン
(少量元素)
・マグネシウム・カリウム・ナトリウム
・塩素・硫黄
「微量ミネラル(9種)」
・鉄・銅・亜鉛・マンガン・セレン
・クロム・モリブデン・コバルト
ミネラルはなんで大切?

ミネラルが大切な理由、それは身体の構成や調節を行ってくれるからです。
確認していきましょう。
身体の構成成分
歯、骨、血液など身体の一部となる組織を構成します。
これが不足してしまうと、身体の正常な機能を保つことが難しくなり、身体に多くの症状として現れやすくなってしまうのです。
体液の調整
カリウムやナトリウム、マグネシウムやカルシウムなどは、身体の中の栄養が一定に保たれるように調整をしてくれます。
むくみなどの問題から病気の症状まで、この体液の調節は非常に大切な機能となります。
酵素の補助
亜鉛や鉄、マグネシウムなどは酵素の補助をしてくれます。
酵素とは、食べたものを消化し、排泄にするまでの課程に関係するものです。
生物が生きていくために欠かせない物質でそれの補助をしてくれるのがミネラルなのです。
筋肉の機能を調節
ミネラルは、筋肉の収縮や弛緩といった機能を調節する役割があります。
特に、マグネシウムは筋肉の弛緩にカルシウムは収縮に働きます。
ミネラルのバランスが悪くなると、筋肉がつりやすくなったり、硬くなる原因にもなります。
不足すると?

ミネラルが不足すると、具体的にどのような症状に陥るのでしょうか?
多くの症状がありますが、ここでは代表的なものをご紹介していきます。
頭痛
頭痛はマグネシウムが不足したり、カリウムとナトリウムのバランスが崩れると起こりやすくなります。
マグネシウムは頭部の筋肉の緊張と血管の痙攣のいずれにも効果があると言われています。
これらを多く含む食材は、海藻類やキノコ類、豆類なので積極的に食べていきましょう。
うつ
最近多いうつ症状なども、ミネラルが不足すると起こりやすくなると言われています。
生活の中に存在する鉛や水銀、カドミウムなどの有害物質などからも影響はありますが、
それらはミネラルの働きを妨げることにも繋がります。
積極的にミネラルを摂取していくことがポイントです。
肩こり
肩こりは筋肉の緊張やそれに伴う血流制限などにも要因があります。
筋肉を和らげる効果はマグネシウムがポイントです。
マグネシウムは、経皮吸収する栄養素なので、にがり(塩化マグネシウムが主成分)などを患部に塗ってマッサージすることもオススメになります。
特に不足しがちなミネラル

不足しがちなミネラルの中でも、特に欠乏しがちなミネラルをご紹介していきます。
マグネシウム
マグネシウムは、身体の中に約25%近く含まれます。
主に骨や筋肉、内臓、脳、血液などに存在します。
糖尿病予防や高血圧予防に効果的な栄養素です。
マグネシウムが欠乏すると、血清中のコレステロールの上昇や中性脂肪の増加、筋肉の拘縮、低カルシウム血症、精神疾患などになりやすくなると言われています。
摂取が多くなってしまった場合は、尿から排泄されるため、過剰症は起こりません。
マグネシウムが多く含まれる食べ物は、
・ナッツ類
・海藻類
・豆類
・玄米など穀類
です。
カリウム
カリウムは、ナトリウムとともに身体の中の調整をしてくれます。
筋肉の調節や酵素の活性化、細胞内の浸透圧の維持などです。
日本人は食生活からナトリウムを多く摂取する傾向があるので、バランスを取るためにもしっかりとカリウムを摂取していく必要があります。
カリウムを多く含む食材は、
・バナナ
・スイカ
・緑黄色野菜
・豆類
などです。
鉄
鉄は多くの人々が不足しやすい栄養素です。
不足すると、貧血や倦怠感などに繋がります。
鉄を多く含む食材は、
・レバー
・お肉
・ほうれん草など緑黄色野菜
です。
亜鉛
亜鉛は、酵素の活性化に関与し、免疫機能の補助などにも効果的です。
また味覚を正常化してくれる働きも亜鉛にはあります。
不足すると、味覚障害や貧血、胃腸機能、免疫機能の低下にも繋がります。
亜鉛が多く含まれている食材は、
・牡蠣
・豆類
・レバー
などです。
ミネラルを多く含む食材

ミネラルをたっぷり含んだ食材って何でしょう?
そのキーワードは、マゴワヤサシイです。
確認していきましょう。
マ・・・豆類

豆類にはミネラルが多く含まれます。
また植物性タンパク質も豊富で、不足しがちな栄養素補うにはもってこいの万能食材。
枝豆、そら豆、えんどう豆、ひよこ豆、いんげん豆などから豆腐まで様々な種類の豆類を摂取していきましょう。
ゴ・・・ごま、ナッツ等種子類

ゴマやナッツはカリウムやマグネシウムが特に多く含まれます。
不足しやすいミネラルを積極的に摂ることが出来るので、とてもいい食材です。
料理に使うだけでなく、間食としても利用することがオススメです。
ワ・・・わかめ、海藻類

ミネラルの王道である海藻類。
同時に水溶性食物繊維も豊富で、便秘改善など腸内を整えてくれる効果があります。
こんぶ、わかめ、ひじき、もずくなどが代表的です。
ヤ・・・野菜、果物

野菜や果物も多くのミネラルを含みます。
野菜を選ぶ際は、色の濃い野菜を選ぶこと。
色が濃い野菜は栄養価が高いものが多いんですね。
キャベツやレタスだけにならず、ブロッコリー、トマト、人参などを加えていきましょう。
サ・・・魚

魚はミネラルたっぷりかつ、タンパク質や良質な油を摂ることが出来ます。
できれば、背の青い魚で、なるべく新鮮な状態で食べることが出来るといいでしょう。
ぜひメイン料理を魚料理にしてみてください。
シ・・・しいたけ、キノコ類

きのこも海藻類と同様に食物繊維が豊富な食材。
ミネラルたっぷりなんですよ。
エリンギ、舞茸、しめじなどが代表的です。
イ・・・芋類

いも類は、ミネラルと同時に多くのビタミンや食物繊維も摂ることができます。
糖質の種類もデンプンを多く含むため、急激に血糖値を上げる心配性はありません。
良質なエネルギーの補給をすることが出来ます。
知って得する、「ミネラルバランス」を知ろう!

ミネラルには「ミネラルバランス」と言った言葉があります。
ただ多くとれば良いというものではなく、そのバランスが大切なんですね。
ここでは特に重要なバランスを3つご紹介します。
①カルシウム:マグネシウムバランス=2:1
②カルシウムリンバランス=1:1
③カリウムナトリウムバランス=5:3
これらのバランスをしっかりと保つことが重要です。
特に前代の食事では、
①だとカルシウム過多、マグネシウム不足
③だとナトリウム過多、カリウム不足
になりやすい傾向があるので、
過多になりやすいミネラルを抑え、不足しがちなミネラルを積極的に摂取するように心がけていきましょう。
バランス良い食事を心がけて

以上、ここまでミネラルについてまとめていきました。
漠然と「ミネラルが大切」という感覚から、少しでもその重要性が理解できたのではないでしょうか。
ミネラルも、他の栄養素と同じように大切なのはバランスです。
一般的には不足しがちな栄養素ですが、
ただたくさん摂取すれば良いというものでもありません。
特に上にも書いた通り、各栄養素の効果を引き出すためには一定のバランスがあり、
そのバランスを意識して食事をとることが大切です。
そのためには偏らずに食事をとっていくこと。
オススメの食事はやはり「マゴワヤサシイ」を多く含む和食です。
和食を中心とした食生活を送り、ミネラルをしっかりと摂りながら、身体の調子を整えていきましょう。